地方競馬予想の基本:初心者が知っておくべき情報ガイド
▼ 知っておくといい初心者も楽しめる地方競馬情報
-
地方競馬初心者ガイド - 楽しみ方と知識の全て
地方競馬の初心者に向けて、「地方競馬の楽しみ方」として情報をまとめましたが、今回は「知っておくべき地方競馬情報」をより詳しくお伝えします。
地方競馬の魅力や特徴、予想のコツを深掘りし、初心者から上級者まで楽しめる内容に仕上げました。
-
地方競馬の基本情報
以前「競馬コラム」で地方競馬について、全3回にわたって解説したことがありますが、今回はさらに詳しい情報を「地方競馬情報の保存版」としてコンテンツ化しました。
地方競馬の大きな特徴として、ナイター開催や場立ち予想師の存在に触れましたが、それ以外にも興味深い特徴があります。❶ ダートの砂厚の違い
❷ 独特のコース形態
❸ ナイター開催
❹ 場立ち予想師の存在大まかにいうとこの4つが特徴と言えます。
例えば盛岡競馬場を除けば地方競馬に芝コースはなく、全競馬場オールダートになりますが、このような初心者 地方競馬トリビアも案外知らない人がいるようなので、これらの特徴を詳しく解説し、地方競馬の魅力を存分にお伝えします。
-
❶ 中央競馬と地方競馬のダート(砂厚)の違い
地方競馬に興味を持つ方なら、「地方競馬のダートの砂は深い」という都市伝説的な話を聞いたことがあるかもしれません。実際にはこれは大きな誤解です。中央競馬の砂厚は8〜8.5cm(海砂)で設定されていますが、大井競馬場などでは7.5cm前後(海砂)と浅めに設定されています。
何故このような都市伝説的な話が流布したかは謎ですが、私も改めて調べてみるまで、地方競馬の砂は深いとなんとなく信じていました。…というのも、中央から地方の交流競争で馬を使う調教師が、いつだったか「地方の深い砂はパワー型のこの馬に合う」と、平気で勘違いしたコメントをしていたのが記憶にあり、てっきり一括りに「地方の砂は深い」と信じていましたし、そう考えている関係者も実際にいるということは、現実問題としてあるようです。
ただ、実際に調べてみると盛岡競馬場の砂厚は12cmに設定されているように、深い競馬場も確かにありますが「地方競馬状の砂は全てが深い」という認識はは間違ってたようで、すべての地方競馬場が深いわけではありません。
競馬場によって千差万別だということが分かります。砂厚の、中央競馬場と地方競馬場の比較
中央競馬場 8~8.5cm 門別競馬場 12cm 盛岡競馬場 12cm 浦和競馬場 9~10cm 船橋競馬場 9cm 大井競馬場 7.5cm 川崎競馬場 8.5cm 金沢競馬場 10cm 笠松競馬場 9cm 名古屋競馬場 10cm 高知競馬場 15cm 前記のように大井競馬場は中央よりも浅い 7.5cmの砂厚に設定されています。
この理由は、調教をコースで行わなければならないため、あまり深い砂で調教をするとパワーが養われるどころか、却って馬の腰や靭帯に負荷がかかりすぎて故障の原因となってしまうことが往々にしてあるからです。…かと思えば、高知競馬場は15cmと相当に深く設定されています。やはり地方競馬予想をやる上で、競馬場の砂厚を事前にチェックしておくことは重要です。
各競馬場を転戦するケースが多い地方馬を比較する場合、どこの競馬場に良績が集中しているかは、馬券検証にあたり欠かせないファクターとなります。
-
❷ 地方競馬場の、独特のコース形態
前項目で「砂厚」一つを取り上げただけでもかなり競馬場ごとに形態に差があるのが地方競馬場です。
これに加え「コース形態」も考慮しなくてはならないとなると、馬券検討はさらに骨の折れる作業となってきます。
ただでさえ情報の少ない地方競馬で、競馬やる人も中央より少ないとなると、(地方競馬が毎日開催されているということで最近増えてきたとはいえ)地方の競馬予想サイトが少ないのは地方競馬予想は予想しづらいからでしょう。
地方競馬の「コース形態」について具体例を挙げてみます。
南関東4競馬場を比較すると、大井競馬場や船橋競馬場のコースは広く、ホームストレッチや直線も長い形態です。これは中央競馬の「大箱」と同じような認識です。
一方、川崎競馬場は「直線がかなり短い」ため、先行馬に有利なコースとされています。
浦和競馬場に至っては「さらに直線が短い」ため、3、4コーナー付近から追い出しが始まる馬も普通に見られます。このように「南関東4競馬場所属の馬」は、これらのコースを主戦場としており、コース形態による得手不得手が極端に現れます。地方競馬予想を行う際には、この独特のコース形態を理解しておくことが非常に重要です。
地方競馬や競馬予想サイトについて知識を深め、的確な予想を立てるためには、これらのポイントを押さえておく必要があります。南関東4競馬場の特徴を把握し、各コースに適した馬を見極めることで、競馬予想の精度を高めることができるでしょう。
-
❸ 地方競馬のナイター開催
「ナイター開催」とは、気候が良い時期に夜間に競馬を開催し、集客力を高めることを目的とした開催形式です。近年、船橋競馬場が通年でナイターを開催することが決定し、大きな話題を呼んでいます。
集客の観点から見ると、中央競馬は「週末の昼間」に開催されるため集客が容易です。一方、地方競馬は基本的に平日に開催されるため、特に昼間の開催では集客が難しいのが現実です。この問題を改善するために導入されたのがナイター開催です。

ナイター開催は、仕事帰りにも競馬場に立ち寄ることが可能になり、帰宅後に自宅でネット投票もできるため、売り上げの向上に寄与します。しかし、ナイター開催には莫大な設備投資が必要です。
南関東4競馬場のうち、大井と川崎は先駆けて春から秋の終盤までナイター開催を行い、集客力の向上に成功しています。これに続けとばかりに、船橋競馬場も今年から通年ナイターを導入し、大井や川崎に負けない集客力を目指しています。
しかし、浦和競馬場に関しては、他の3競馬場に比べて立地的に集客が難しいため、ナイター設備の導入は現実的には厳しい状況です。ナイター開催は、地方競馬の集客力向上と売上増加に効果的な手段ですが、設備投資の負担も考慮する必要があります。地方競馬の発展には、これらの課題を克服することが重要です。
-
❹ 地方競馬の場立ち予想師の存在
地方競馬には、中央競馬にはない独自の制度として「公認予想師」の開業が許可されています。
これは昔からの風習であり、新聞だけでは情報が乏しい地方競馬を、来場者により深く理解してもらうために設けられた地方競馬ならではの制度と言えます。
各競馬場には名物予想師と呼ばれる人々がいます。
その中でも群を抜く集客力を誇るのが、大井競馬場で開業してる「ゲートイン」の屋号で有名なカリスマ予想師、吉富隆安氏です。彼は全国的に知られる存在で、多くの競馬ファンに愛されています。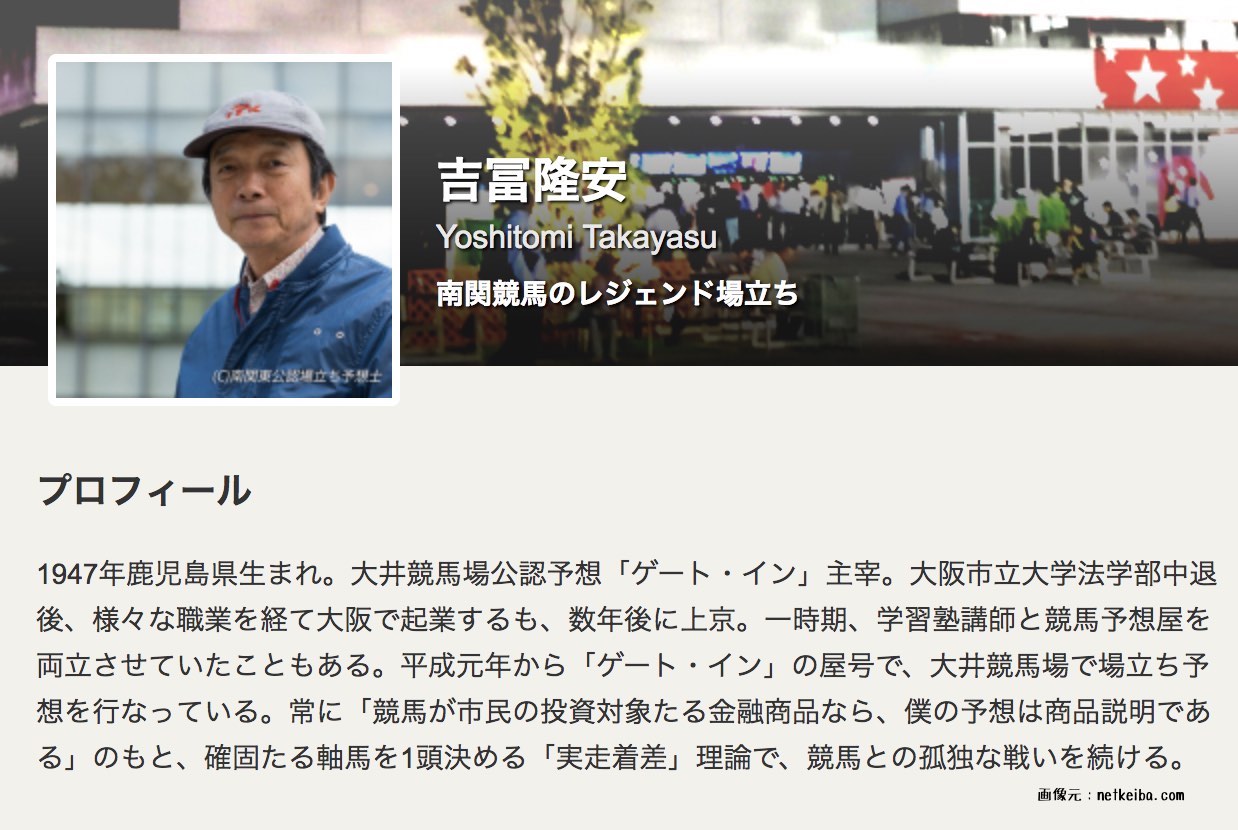
↑大井競馬場の「ゲートイン」吉富隆安氏 「公認予想師」は競馬用語で「場立ち」とも呼ばれます。
吉富隆安氏は川崎競馬場でキャリアをスタートさせ、アメリカで開発されたアンドリューベイヤー理論(実走着差理論)を日本向けに改良し、徐々に頭角を現しました。彼はの競馬理論は非常にしっかりしており、圧倒的な的中率で知られています。私も何度か彼を見たことがありますが、その精度の高さには毎回感動させられました。
そこに輪をかけるように落語家顔負けの口上も見事なもので、的中率の高さと相まって川崎競馬場で爆発的な人気を博しており、私は感動したものでした。その人気は川崎競馬場だけに留まらず、主戦場を大井競馬場に移し、現在に至ります。
▲ 場立ち予想士の仕事に迫る(netekiba) 吉富隆安氏のカリスマ性はJRAも認めており、netkeibaでも彼を高く評価しています。
過去には有馬記念のパンフレットに寄稿されるほどで、近年ではNHKの番組にも取り上げられるなど、その影響力はますます拡大しています。彼の予想は年を追うごとに円熟味を増し、今やカリスマの域を超えていると言っても過言ではありません。もし機会があれば、ぜひ一度吉富隆安氏の予想に触れるために大井競馬場に足を運んでみてください。そのエネルギーと、まるで芝居を見ているかのような口上に圧倒されることでしょう。見る価値のある素晴らしい体験が待っています。
地方競馬情報の詳細を知るには
JRAの馬の成績はJRAの公式サイトで確認できますが、「南関東公営競馬」に所属する馬の成績を知りたい場合には、南関東4競馬場の情報を提供している「nankankeiba.com」が便利です。

▲ 地方競馬の馬柱はココで見れる リンク→南関東4競馬場公式サイト nankankeiba.com 「nankankeiba.com」では、開催日や開催時間(昼開催かナイター開催かなど)も確認できます。地方競馬の情報をどこで確認すればいいか分からない方も、新聞がなくても「nankankeiba.com」を利用すれば、馬柱や詳細な成績情報を簡単に確認できます。
地方競馬の情報を効率よく収集し、的確な予想を立てるために、ぜひ「nankankeiba.com」を活用してみてください。
-
地方競馬の賞金事情〜中央競馬と世界との比較
地方競馬の賞金事情
地方競馬の賞金額は中央競馬に比べて格段に低いですが、ミルコ・デムーロ騎手は「イタリア競馬の賞金は大井競馬の賞金とほぼ同じくらい」とコメントしていました。その大井競馬場は国内の地方競馬場で最も高い賞金を誇っています。
南関東4競馬場の中でも微妙な格差があり、各クラスの賞金は同じでも、集客数という点で大井競馬場がダントツであるため、最も多くの賞金を負担できる大井競馬場に開催が集中しています。その結果、浦和競馬場は開催が少ないという現実があります。
大井競馬場はJRA並みにコラボイベントにも力を入れており、常設のライブステージも設置されています。
G1などの大きなレースの際には音楽やお笑いのライブも行われ、人気絶頂期のレイザーラモンのライブでは、私も観ましたが観客が大変な賑わいを見せていました。
-
大井競馬場の高額賞金と世界の競馬事情
地方競馬で最も高額な賞金を誇るレースは、年末に行われる東京大賞典で、その賞金は第69回(令和5年)から8,000万円から1億円に増額されました。ちなみに2着3500万円、3着2000万円、4着1000万円、5着500万円です。
同様に地方競馬の祭典と言われるJBCクラシックも、以前は8000万円でしたが、2022年に1着賞金が1億円に増額され創設時の賞金に戻りました。これは集客力の影響も考慮された結果です。
ちなみに、中央競馬のJRAでは有馬記念の2023年の賞金は1着5億円、2着2億円、3着1億3000万円、4着7500万円、5着5000万円でした。やはり中央競馬と地方競馬の賞金には大きな差があります。
世界を見てみると、ドバイワールドカップの賞金は10億円で、アメリカのペガサスワールドカップは出走する馬が1億円の参加料を払います。世界の競馬は桁違いの賞金を誇っています。
日本のクラシックレースも登録料が必要で、重賞では第1回が2万円、第2回が8万円、G1では第1回が6万円、第2回が24万円、クラシックでは第1回が1万円、第2回が3万円、第3回が36万円、追加登録の場合は200万円かかります。しかし、やはり世界の競馬と比べると桁が違うことが実感されます。
-
中央競馬の騎手を凌駕する、地方競馬
「交流元年」から見る地方競馬の実力とJRAの反発
地方競馬と中央競馬には「交流競走」という日があります。この「交流競走」の日には、中央馬が地方のレースに参加できる日となります。
南関東以外の地方競馬場でも、地方競馬は主に「水曜」に交流重賞や交流競走が組まれることが多く、その際には交流競走に騎乗する騎手はその日のレースに参加できるというルールです。しかし、残念ながら実際には中央の騎手が地方馬に乗る機会はほとんどありません。
理由は、中央に比べて賞金の低い地方競馬のレースに中央競馬所属の騎手を乗せることが、地方競馬の騎手界の反発を招くからです。武豊、デムーロ、ルメールといったトップジョッキーも例外ではなく、1日1鞍の騎乗で終わることも普通にあります。ただし、例外として内田博幸騎手と戸崎圭太騎手がいます。彼らは元・南関東所属であり、南関関係者とのパイプが今も厚く、南関競馬を支えた功労者として積極的に騎乗依頼が来ています。
水曜日に大井で交流重賞がある際には、中央の騎手も重賞以外の交流競走に参加しますが、中央の馬には中央の騎手が乗ることが一般的です。地方の馬に中央の騎手が乗ることはほとんどなく、その点で内田博幸騎手と戸崎圭太騎手は例外的に騎乗依頼を受けることが多いのです。現在、地方と中央の交流戦のルールは概ね固まりましたが、ここに至るまでには多くの「しがらみ」が交錯してきました。
私も知識の裏付けのために調べましたが、昭和の時代には地方の騎手が中央のレースに乗ることはほとんど稀でした。しかし、1995年に「交流元年」と称され、中央競馬と地方競馬間の交流が大幅に拡大されました。
地方主催で行う中央との交流重賞の整備や、条件付きではありましたが地方在籍のままでの中央GI競走への出走が可能となりました。
-
地方ジョッキーが中央を超える現象
「交流元年」により、地方競馬所属の騎手が中央のレースに乗る機会が一気に増えました。その中で、地方の騎手が中央の騎手を質・量ともに凌駕する現象が発生しました。
その代表的な騎手が「アンカツ」こと安藤勝己元騎手です。

▲「アンカツ」こと安藤勝己元騎手 地方競馬、当時笠松所属の騎手として脂がのりきっていた安藤勝己騎手は、中央のレースで勝ちまくり、1997年からは地方所属馬が出走できる中央競走枠が大幅に増加したこともあり、1999年には455戦55勝という成績を挙げました。
この頃より「アンカツ」のニックネームが中央ファンの間にも完全に浸透しました。この結果、地方に在籍しつつ騎乗機会の少ない中で55勝を挙げた安藤勝己騎手に対して、2002年7月、JRAは騎手免許試験の取り扱いを一部変更し、「受験年の前年以前の5年間において、中央で年間20勝以上の成績を2回以上収めている騎手に対しては騎乗技術試験を免除する」という新要項を発表しました。
当時、地方騎手でこの基準を満たしていたのは安藤勝己騎手のみで、この基準が後に「アンカツルール」と呼ばれるようになりました。
そして安藤勝己騎手が先鞭をつけた地方騎手の移籍、いわゆる「アンカツルール」に続いたのが岩田康誠騎手と内田博幸騎手です。彼らは中央競馬移籍直後から勝ちまくり、その影響で中央騎手会が慌てて「鎖国政策」を作る事態になりました。
-
中央騎手会が慌てて作った「鎖国政策」
これに危機感を抱いたのが中央の騎手会で、地方から凄腕がバンバン中央に流れてきたら新人騎手の騎乗機会が失われ、技術が育たないという意見が噴出しました。
そこで中央の騎手会は、地方からの凄腕騎手の流入を制限し、JRAの新人騎手の騎乗機会を確保するために、2010年以降、「受験年の前年以前の5年間において、中央で年間20勝以上の成績を2回以上収めている騎手」に対しても1次試験受験を必須とし、新たに直近3年以内にJRAで年間20勝2回の成績を収めた騎手のみが2次試験の実技を免除され、口頭試験のみとなる新規定を設けました。
この規定により、戸崎圭太騎手は10年と12年に22勝を挙げたため、2次試験の面接のみでJRAの騎手となりましたが、以降は地方騎手の中央への門戸が狭まり、「交流元年」という文句自体が尻すぼみとなりました。
現在では「戸崎で最後になる」と言われるほどに、地方騎手の中央への移籍は難しくなっています。JRAの既得権益を守るための「鎖国政策」とも言えるこのルールにより、中央の騎手の地位が守られています。
日に何本も騎乗して鍛え上げられた地方ジョッキーは、アンカツや内田、岩田などの地方ジョッキーが中央に来たことで、地方のジョッキーの腕が武豊に勝るとも劣らないことが証明されました。このまま開国を続ければ中堅以下の若手騎手の騎乗機会が失われることを懸念し、中央競馬側は「蛇口を締める」対策を取ったのです。
もちろん、賞金の部分も関係していると思いますが、「地方のジョッキーの方が上手い」というイメージがこれ以上広がるのはまずいと考えた結果でもあります。実際に関係者はその腕前を認識していますし、だからこそ地方競馬は見ていて非常に面白いのです。
地方競馬を見ていると、地方の一流どころの騎手を積極的に乗せたい馬主や調教師の本音が見えてきますが、JRAの騎手が「組合」という防波堤で対抗している感じがします。デムーロやルメールも、漢字の読み書きができなければ合格しないという厳しい試験制度も存在します。
-
地方競馬の気になるところ
地方競馬Q&A:トップ3の疑問解決
❶ 地方専用の厩舎はあるのか?
❷ 中央で成績が悪い馬は地方に行けるのか?
❸ 騎手の違いは?❶ 地方専用の厩舎はあるのか?
多くの人が知らないかもしれませんが、南関東4競馬場には競馬場内に厩舎が併設されています。
しかし、競馬場内に馬が収まりきらない場合には、認定厩舎制度が存在します。
南関東4競馬場から認定を受けた施設だけが厩舎を設置することが可能です。2018年6月時点で認定を受けている施設は、以下の3つだけです。・野田トレセン(浦和競馬場認定)
・小林牧場(大井競馬場認定)
・小向厩舎(川崎競馬場認定)この3つの施設は、南関東4競馬場が認定しており、競馬場内で調教するよりも高度な調教施設を有する場合もあります。特に大井競馬場が認定している小林牧場は、坂路コースを利用した調教が可能で、競馬場内の厩舎よりも充実した施設です。
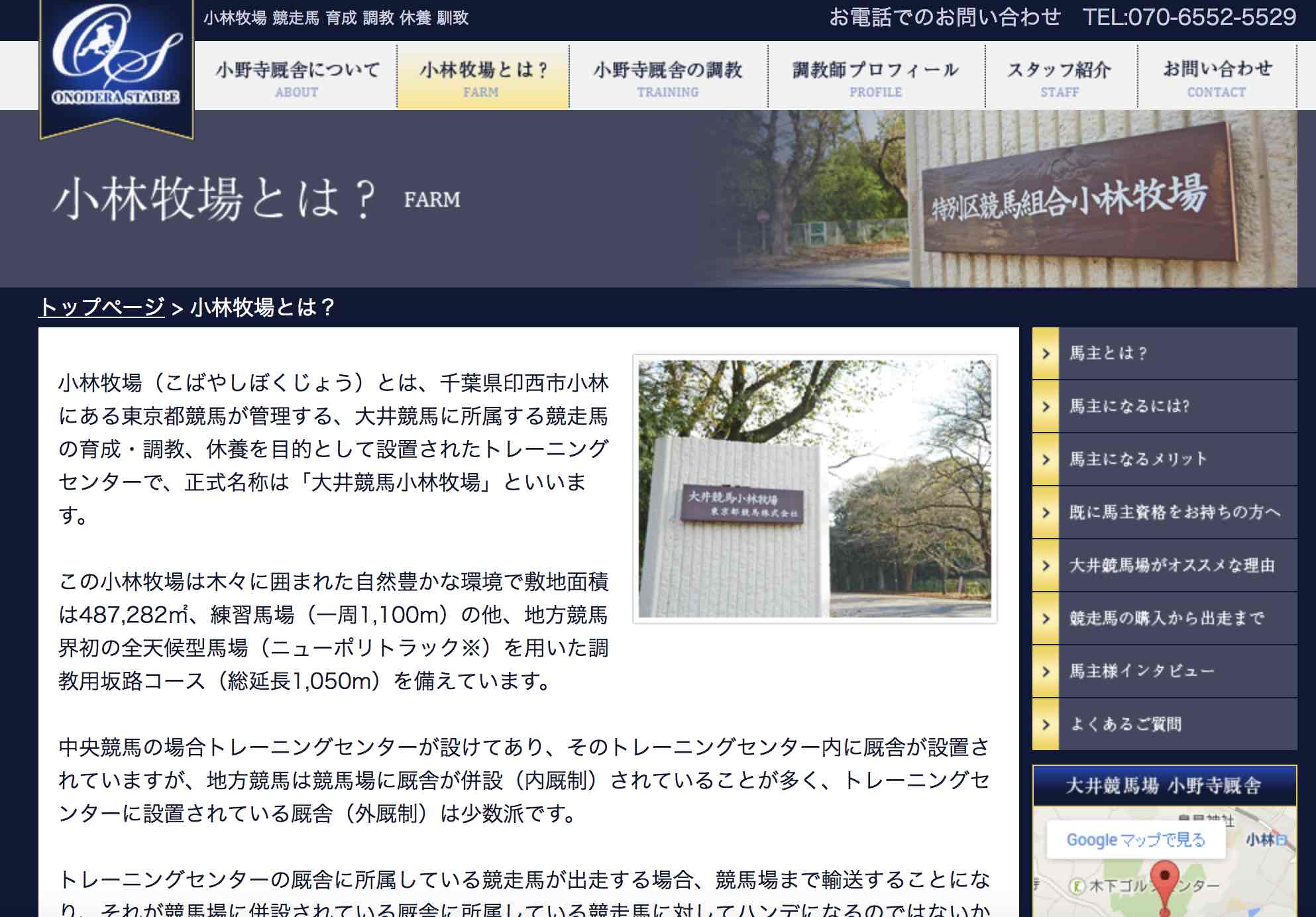
また、地方競馬教養センターという施設が栃木県那須市にあり、ここでは騎手候補生や調教師、厩務員などを育成しています。この施設も地方競馬の外厩として認定されており、中央競馬でいう「競馬学校」と同様に高度な調教施設を備えています。
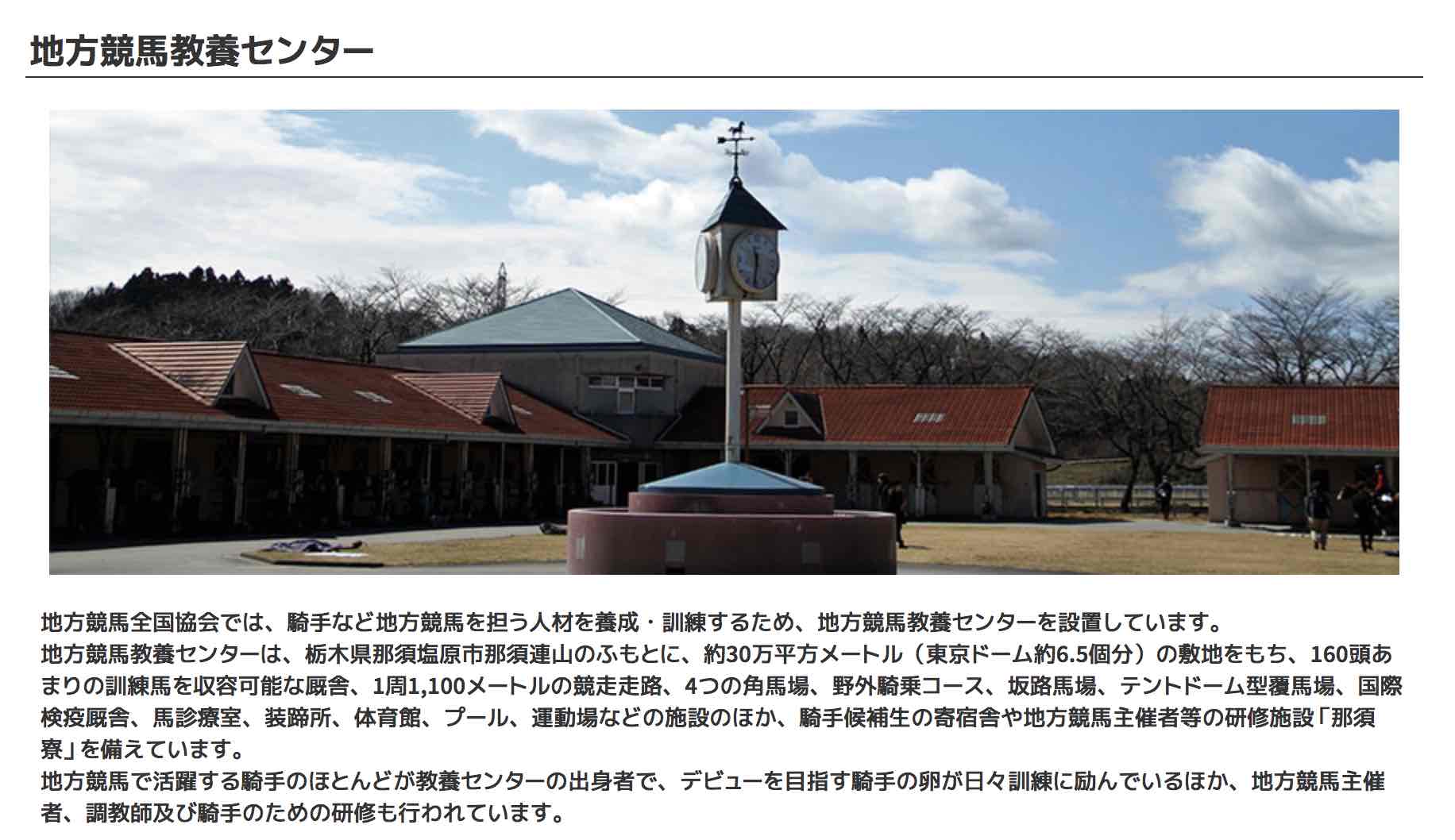
▲ 地方競馬教養センター
-
❷ 中央で成績が悪い馬は地方で走る?
パターン1:中央から地方へ
3歳馬がスーパー未勝利戦で勝ち上がれず、出走できるレースがなくなった場合、現役を続行するために地方の厩舎に転厩することがあります。この場合、「地方で2勝」すると中央への再転入が可能になります。
500万条件への出走が可能ですが、中央の1勝馬と比較すると抽選で弾かれることが多いのが現状です。しかし、500万条件を1度勝てば、中央の2勝馬と同格になります。
パターン2:中央から地方へ
ダートのオープンで頭打ちになった馬が地方に転厩するケースもあります。
ダートの条件戦を勝ち上がり、オープンに昇級して1勝することはできたものの、賞金加算できずに除外が続く場合、地方競馬に転出することがあります。例えば、中央から船橋に移籍して息を吹き返したキタサンミカヅキの例が挙げられます。
-
❸ 騎手の違いは?
中央と地方は騎手試験の難易度の違いから、中央の騎手試験は非常にレベルが高く、規制も厳しいです。
中央の試験に受からなかった騎手候補生が地方の試験を受けるケースもあります。
騎手人生の「入口」の部分ではこの違いが存在しますが、地方である程度の成績を積み重ねて騎乗機会が増えるようになれば、地方競馬の騎手は騎乗機会が多く、その分だけ技術が磨かれるため、中央の騎手よりも技術が上と一般的には見なされています。一昔前は、そもそも技術を比較すること自体が困難でしたが、地方競馬と中央競馬の交流が始まった「交流元年」により、地方のトップジョッキーであったアンカツや内田博、岩田、戸崎が大活躍したことで、地方所属騎手の力量が広く認識されるようになりました。
中央の騎手、例えば武豊が週末に最大24レースに騎乗するのに対し、地方の騎手南、関東の内田博や戸崎は週に5日開催されるため、最大60レースに騎乗することが可能です。
この場数の差が経験値の向上に繋がります。また、地方馬は「乗りにくく、癖が多い」ことが多く、そうした馬を扱うことで地方のジョッキーの方が技術を磨いています。
このような背景から、馬には申し訳ない例えだが騎手に関して言えば「温室育ち」と「雑草」の違いと言っても過言ではないでしょう。
地方競馬もその面白さをぜひ楽しんでみてください。



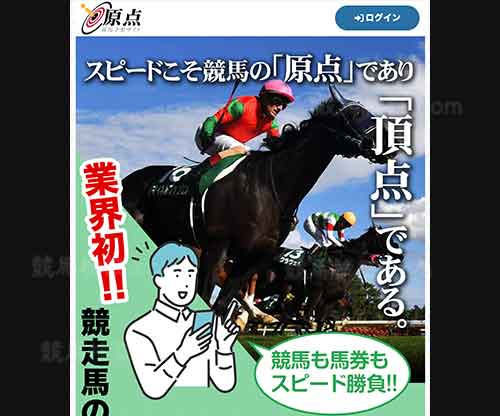













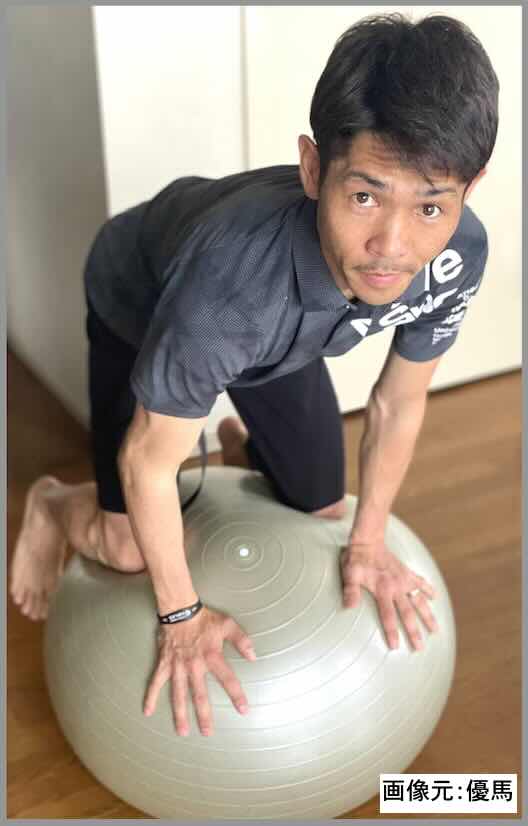

7/21にはなんと、わずか20pt予想(2000円)で参加できるコースで、福島4Rにて477.2倍、50倍、29倍の3券種的中した。…仮に500円で全て買ってたら、今回は2000円予想で合計27万 8100円の配当だ。
数年前には1000円予想の3237.5倍他全2券種的中といい、すごい。…因みに過去最強は、1000円予想で当てた6479.2倍だ(コレ)。